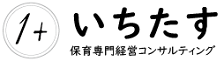この度、2025年7月15日(火)にABEMA NEWSチャンネルで放送された「ABEMA PRIME(アベプラ)」に、弊社代表取締役の大窪由衣が、幼児教育・保育業界の専門家として生出演いたしました。
「ABEMA PRIME(アベプラ)」には、田村淳さん、パックンさん、茂木健一郎さん、てぃ先生が出演されており、弊社代表取締役はゲスト出演という形でお声がけをいただきました。弊社以外には、保育園の運営サポートを行う、株式会社シェンゲン執行役員の葛尾健太様もゲスト出演されていました。
出演したのは、「倒産が最多ペース?保育園の2025年問題」という、幼保業界が直面している重要なテーマを取り上げたコーナーです。
番組では、保育園の倒産が過去最多となっているニュースの背景や、人手不足の現状について深く掘り下げられました。放送時間内ではお伝えしきれなかった弊社の考えや、この問題に対する具体的な提言について、本記事で詳しくまとめております。ぜひ最後までご覧いただければ幸いです。
また、今回の放送内容は、ABEMAビデオでご視聴いただけます。見逃してしまった方も、ぜひこの機会にご覧くださいませ。
ABEMA Prime #アベプラ【公式】のYoutubeにも、今回の放送内容が公開されています。ノーカット版ではありませんが、ABEMAビデオの視聴が叶わない方も、ぜひこちらをご視聴くださいませ。
Yahoo!ニュースにも今回の放送内容が取り上げられています。Yahoo!ニュースのコメント欄には、2025年7月24日時点で500件を超えるコメントが寄せられ、保育園の今後について高い関心を抱く方の多さを感じました。

アベプラという素晴らしい場で、田村淳さん、パックンさん、茂木健一郎さん、てぃ先生といった著名な方々と、約30分にわたって幼児教育・保育業界について深く語り合えたことは、私たちにとっても大変貴重な経験となりました。このような影響力のある方々と共に、業界の現状や課題について発信できたことは、幼児教育・保育業界全体の未来にとっても、大きな一歩になると勝手ながら確信しています。
保育園倒産ニュースの概要

まずは保育園の倒産についてのニュースを紹介します。
番組出演のきっかけとなったのが、株式会社帝国データバンクが2025年7月9日に公表した「保育園」運営事業者の倒産動向についてのレポートです。内容を簡潔にまとめると、以下のようになります。
- 2025年上半期に発生した倒産や休廃業件数は22件
- 上記件数は前年同期の13件の7割増、通期で過去最多を更新する見通し
- 特に中小規模の保育園で運営困難となるケースが増加
- 2023年度における「業績悪化」の割合は54.3%と半数超
- 少子化を背景に児童数の減少、保育士不足、食材費等のコスト高騰が要因
(出典:株式会社帝国データバンク 「保育園」の倒産・休廃業解散動向(2025年上半期))
さらに、上記レポートでは、既に保育施設が余剰となっている地域もあり、今後も淘汰が続くと予想されています。
この深刻なニュースを受け、アベプラより「倒産が最多ペース?保育園の2025年問題」というテーマでの出演依頼をいただきました。そして、ABEMA PRIME(アベプラ)への出演を機に保育園倒産について真剣に向き合った内容を皆様の疑問にお答えする形で、Q&A形式で弊社の見解をまとめましたので、ぜひご覧ください。
いちたすが考える「保育園倒産」
ここからは、番組で語りきれなかった内容も深掘りしつつ、幼児教育・保育業界専門の経営コンサルティングを行う弊社が考える「保育園倒産問題」について、Q&A形式でお答えしていきます。
なぜ保育園の倒産が増えているのか


上半期で22件と、このままでは過去最多のペースで倒産が増えています。そもそも、なぜ倒産が増えているのでしょうか。

待機児童解消のために保育園を増やしたものの、想定※以上に少子化が進んで、園児が集まらず経営が悪化しています。また、保育士不足も重なり、運営を継続できなくなっているためだと考えます。
国立社会保障・人口問題研究所が公表した予測から15年早いスペースで少子化が進んでいる

今後、保育園側も“選ばれる努力”をしていかないといけない時代になりますか?

施設の定員数よりも子どもの数が少ない時代になっているので、保護者や職員から求められなければ残念ながら、地域での役割は終了してしまう可能性があります。

保育園過多になる将来は予想できなかったのですか?

業界の経営者に限って説明すると、2通りに分かれると考えています。
予想せずに楽観的に保育事業に参入された方もいれば、今後競争が激化した時に備えて、園児を預かる幅を広げておきたい、そのために新規園を創設しておこうと考えられた経営者もいます。
弊社のお客様は後者が多いです。

儲かると踏んで参入した企業も多いですか?淘汰の時代がきている?

おっしゃる通り、民間企業の参入時、楽に運営できる補助金ビジネスと捉える方も多かったのではないかと思います。新しく建物を建てる時に施設整備の補助金が出る事業は珍しかったのも影響しているかもしれません。
しかし、今は定員割れする施設が多いので、これからは園運営に真剣な園しか残らないと思います。

保育園経営は儲かるのか?

制度を正しく理解し、コンプライアンスを守りながら、適切に運営することが出来れば、利益は残ります。
利益が残ることで、保育士の給与を上げて、子どもたちのための環境整備に投資が出来る様になります。
理念も大切ですが、利益も同様に大切だと考えています。
今後の保育園倒産の動き


待機児童問題で「保育園を作りすぎた」ということですか?

おっしゃる通りです。
国は平成25年度の「待機児童解消化プラン」から令和6年度末までの「新子育て安心プラン」のなかで、保育の受け皿を増やすことに数値目標を設けて進めてきましたが、コロナ禍もあり、想定よりも出生数が増えず、結果的に保育の受け皿を増やし過ぎたという実態があります。
いまでも統計上は待機児童として現れない隠れ待機児童の問題がありますし、地域によって増やし過ぎた地域と、まだ十分に供給が足りていない地域が分かれています。

3年連続で倒産増加。倒産はいつまで続くと予想しますか?

子どもを預けたい保護者と受け皿としての保育施設の均衡が保たれるまでは続くのではないかと予測しています。
地域差はありますが、年々出生数は減少し、資金繰りが厳しくなっている法人も増えていると感じますので、むしろこれから閉園は増えるのではないかと思います。

どういう保育園が倒産していますか?

制度の理解が不十分な園です。
保育事業は補助金事業ですので、制度の理解が不十分だと充分利益が確保出来ず、利益が確保出来ないと、職員採用に遅れを取りますし、採用が出来ないと子どもを預かれないので負のスパイラルに入ってしまいます。
保育環境の整備にも投資が出来ないので保護者からも指名されなくなります。

赤字になる前に閉園する保育園もある?

おっしゃる通り、あります。
事業の特性上、突然、閉鎖をすることは難しいですが、預かる人数を徐々に減らして、計画的縮小を行う園もありますし、事業売却案件で保育園の譲渡が出ていることもあります。

保育園の倒産傾向に地域差(都会or地方)はありますか?

あります。
人口が少ない地方のほうが少子化が進むのが早く、保育士の母数も少ないので運営が立ち行かなくなる園が多く見受けられます。
地方は特に子どもの数が減っており、保育園の収入は補助金で賄われているため、子どもの数が減少すると収入が小さくなります。
また、保育士を思うように採用出来なければ、人材紹介会社等の採用に支払う手数料等も大きくなり、経費が大きくなります。
保育士に関係する経費に関しては都会も地方も同様の考え方です。

とは言え…数が足りているなら淘汰されるのは当然と考えますか?

都会と地方で対応が分かれると思います。
都会の場合、保護者の選択肢が複数ある場合は園児獲得競争で淘汰されてしまうことがあると思いますが、それは一般企業でも同じなので仕方が無いと考えています。本気の園だけ残ると思います。

保育園が無い地域が出るのはインフラとして問題があるでしょうか。

人口が少ない地方においては、地域自体のチカラを持続させていくためには、存続させるべきだと思います。
通勤前に車で30分掛けて子どもを保育園に預ける等の無理が出て来ると、地域自体が衰退してしまいます。
少ない労働人口を有効に活用するといった観点から考えると、ある程度は存続させなければいけないのではないでしょうか。
一方で保育園の数が多い自治体で保護者の選択肢が複数ある場合は園児獲得競争で淘汰されてしまうことがあると思いますが、それは一般企業でも同じなので仕方が無いと考えています。

急に倒産すると…子どもや保護者にも影響がありますよね?

共働き世帯にとっては急に閉園になると、会社に出勤出来なくなってしまうので影響が大きいと思います。

今、保育事業に新規参入の相談はありますか?

儲けたいというよりは、保育に情熱がある方が自分の園を設立したいということが多いです。
その場合、保育園を設置したい地域に属する市町村の担当者に事前相談する様に促しています。
いくら情熱があって、保育園を作りたくても待機児童がいないと難しいです。
また、世間でこれだけ少子化が騒がれているので、儲けたいだけの人は斜陽業界として、新規参入しないのではないかと思います。

生き残る保育園の条件とはなんだと思いますか?どうすれば選ばれる保育園になりますか?

ブランディングに力を入れることだと考えています。
子どもの人権や安心安全の保障、質の高い保育を行うのが保育園の共通の使命かと思いますが、そこに自分たち独自の強みといった色をのせ、発信、行動まで一貫している園は、保護者や職員から求められると思います。

倒産も増えているが施設数も増えていますか?

現在でも、新しい保育園の新設の公募はありますが、数年前に比べると、減ってきていると思います。
保育所の施設数としては減ってきていますが、保育所から認定こども園に移行するケースもありますので、令和6年4月時点では、保育施設数としては増えています。
課題は「保育士不足」


保育士の数自体は増えていますか?

一般社団法人全国保育士養成協議会の資料では、2019年の688校をピークに、2022年には668校に減少しているとのことですので、資格保有者はともかく、現役で保育士として活躍される方は減少している認識です。

保育園の数が減っている今人材獲得競争は減。ということは人材不足解消ではないのですか?

保育士不足は現在も続いていますし、より切迫感が出てきています。
倒産が増えているとはいえ、保育施設の数としてはほぼ変わっていないということもありますが、保育士に限らず全業種で人手不足が進み、保育士資格を持っていても保育園で働かず、別業種で働く方も増えているため、ますます保育士不足は進んでいると感じます。
不適切保育を行っている園が大きく取り上げられるなど、保育園に向けられる目が厳しくなり、身内から保育士になるのを止められたという話も聞いたことがあります。

経済同友会の発言※どう思いますか?

一概に人手が増えると解消される問題だとは考えていません。
現場の先生たちと接していると、保育に対する熱い想いがあり、チームで学びを深め、切磋琢磨されていることがほとんどで、同じように想いがある方で無いと難しいのでは?と思います。
経済同友会が6月10日に少子化対策に関する提言として、特定技能1号2号の対象産業に保育を追加する等、外国人保育士の受入拡大を提言。

とは言え、まずは 人手を増やすことが最優先ではありませんか?

いきなり外国人の雇用ではなく、潜在保育士の掘り起こしなどに力を入れられないか?と思います。
保育施設は子どもを預かるだけの施設ではなく、子どもの成長の伴走者なので日本人の代わりに外国人をという発想には違和感を感じます。

それよりも処遇改善の方が先決ということですか? どういう対策が必要ですか?

保育士の退職理由の第一位が人間関係だと伺います。
子どもたちと同じように大人の心理的安全性が確保され、自分らしく活躍出来る社風であり、処遇改善などの手当を適切に受け取れると分かれば人が集まるのではないでしょうか。

保育士の適切な給与とは、どのくらいですか?

こども家庭庁が行った経営実態調査では、保育士の年収は約400万円でした。以前に比べると大きく上がってはいますが、地域差も大きく影響しますので、一概にいくら、ということは難しいと考えています。
ただ、地方の園では、近隣の企業に比べてもしっかりと高くなっている、ということも増えてきています。

外国人保育士…何が問題なのでしょうか? どういう研修が必要だと思いますか?

現場の先生と接していて感じる事は、保育士は専門職だと思っています。
日本人でも難しいのに、外国人で補充しようは難しいではないかと思います。
最低限、保育士の方々と同じ内容を学んだ上で、プラスアルファ必要なことを洗い出すしかないのではないでしょうか…

保育には情熱が必要…やる気のある人なら問題ありませんか?

先ほどの回答と重複しますが、現役の日本人保育士さん達と同じレベルの保育、仲間とのコミュニケーションが円滑な場合は可能性があるかもしれないと思います。

「スキマ保育士」も…急に当日 働ける仕事ではない?

お客様の園に伺っていて思いますが、独自の保育理論はすぐには身に付かないので、即戦力というよりは、入社後のミスマッチを減らすためのインターン制度と捉えるといかがでしょうか。
保育所等におけるスポットワーク(いわゆるスキマバイト)で採用された保育士の取扱いについて、こども家庭庁は最低基準上の保育士定数の一部に充てることは望ましくないとしている。
(出典:こども家庭庁 保育所等におけるスポットワーク(いわゆるスキマバイト)により
採用された保育士の取扱いについて(通知))
まとめ

ここまで、ABEMA PRIME出演について、帝国データバンクのレポートが示す保育園倒産の現状、そして幼保業界専門コンサルティングを行う弊社の視点でのQ&Aまでの内容をお届けしました。
少子化、保育士不足、物価高騰と、幼保業界は大きな課題に直面しています。しかし、私たちはこの課題に真摯に向き合い、明るい未来のために解決策を探り続ける必要があります。
本記事が、幼保業界の経営者の皆様にとって、経営を見つめ直すきっかけとなれば幸いです。ABEMAビデオでの番組無料視聴も、ぜひお見逃しなく。これからも弊社は、幼保業界の皆様のお役に立てるよう、情報発信と具体的な支援を続けてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。