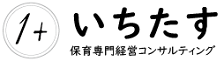少子化がますます進む現状、これまでと同じ方法で園運営を行っていると、運営が苦しくなっていきます。
実際、幼稚園では令和5年度に向けての園児募集が例年に比べてうまく進まなかったという園がとても多くなりました。
現在は、幼稚園での園児の定員割れが大きく取り上げられていますが、保育園・こども園でも同じことが起きてきます。
本記事では、保育園経営の6つの重要改善ポイントとその解決方法について詳しく説明しています。
コンサルタントに任せるなど、外部に依頼した場合の具体的な料金についてもあわせてまとめています。

重要改善ポイントは、当社(株式会社いちたす)のサービスメニューと重なる部分が多くあります。
当社では、創業当時から現在行っている事業を行っていたわけではなく、「寝る間を惜しんで働かれている経営者の力になりたい」という想いから出発しています。
当社のサービスメニューは、保育園経営者からのご要望に対応するために増えてきました。
保育園経営者が抱える問題と6つの重要改善ポイント

保育園経営者が抱える問題は多種多様です。
ですが、経営コンサルタントとして保育園のご提案に入る際、保育園経営者の方が悩まれている事は、6つにまとめる事が出来ると感じています。
- 今後どのように運営していけばよいか【経営戦略立案支援】
- 漠然とした経営計画はあるが、数字に落とし込めていない【財務支援】
- 保育士や職員をどのようにマネジメントしていけばよいのか【マネジメント支援】
- 事務職員が退職したが、引継ぎがうまくいっていない【会計支援】
- 給付費(委託費)や補助金はしっかりと取れているのか【収入最大化】
- 後継者や園長をどのように育てていけばよいのか【教育・育成支援】
多くの方は上記の様な、保育とは別のことに頭を悩ませています。
保育園については、一般的な事業と違い「ネットで検索しても答えが無い」ことや「相談先が少ない」というケースが多いです。
また、保育事業に関する制度や事務手続きに関する書籍も、とても少ないです。
保育園経営者は悩みを多く抱えていますが、相談先が圧倒的に少ないということが、保育園経営者の悩みを深刻化させています。

保育園の運営については、都道府県や市町村で独自のルールや重点項目があるので、国が出している資料と、市町村の担当者では、言っていることが違う、ということがよくあります。
個別の話も多いため、なかなか書籍が少なく、相談先も少ないのが現状ですが、「相談する先が少ない」「誰かに任せられない」ということは、保育園経営者がご自身で経営に対する意思決定を行う必要があるということになってしまいます。
保育園経営者が抱える問題とは?

保育園経営者から寄せられた、具体的なお困り事を3つご紹介します。
一つ目は、園児数の減少に伴い、園経営が赤字になってしまうケースです。
園を縮小しなければいけないとさえ感じています。
市町村が、個別に「法人にとって最適なアドバイス」をする事はほとんどありませんので、経営者A様のお金の悩みを解決する方法としては、加算の見直しや、定員設定の変更など、検討する必要があります。
二つ目は、処遇改善等加算についてです。
処遇改善等加算についてのお問い合わせは、よく頂きます。特に多いのが、処遇改善等加算の制度に対するご質問や配分方法です。
こんな事なら、最初からもらわなければ良かったと思います。
処遇改善等加算Ⅱを取得せずに、保育士の雇用において、他の保育所やこども園に遅れを取らないと言えるでしょうか?
当社のお客様も経営者B様の様にヒトの悩みを多く抱えられていました。
当初は処遇改善等加算Ⅱを取得するか否かを悩まれているお客様も多くいましたが、当社がご支援に入ることで、今では職員に適正に加算額を配分し、保育士の求人も上手く回り始めている園が増えています。
処遇改善等加算Ⅱについて、詳しくは以下の記事をご参照ください。
参考記事:【プロが解説】処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱとは?全体像と手当の実態
三つ目は、書類仕事など、次々と変わる制度や申請・実績報告に対応することで、いっぱいいっぱいになってしまっているケースです。
もっと保育の事を考えるための時間が欲しいです。
法人にとって「経営者に時間がない」という事は深刻な問題です。
運営に支障が出ない様に、早急にご自身の業務を引き継ぐか、外部に委託するか等を検討する必要があります。

上記のようなお悩みは、本記事を読まれている方にとっても、共感できる部分があるのではないでしょうか。
企業経営を行う上では、ヒト・モノ・カネ・情報が大事と言われますが、保育園経営では、ヒトに対する問題がクローズアップされがちです。もちろん、ヒトが大事なことは言うまでもありませんが、経営を行う上では、ヒトだけにフォーカスせず、全体を見ることも必要です。
3つのお悩み事については、本記事後半の「保育園経営コンサル事例」にて、どのように解決したのかをご紹介しています。
保育園経営6つの重要改善ポイント

上の項目では、保育園経営における3つのお困りごとを見てきましたが、ここでは、保育園経営における6つの重要改善ポイントについて、詳しく見ていきます。
- 今後どのように運営していけばよいか【経営戦略立案支援】
- 漠然とした経営計画はあるが、数字に落とし込めていない【財務支援】
- 保育士や職員をどのようにマネジメントしていけばよいのか【マネジメント支援】
- 事務職員が退職したが、引継ぎがうまくいっていない【会計支援】
- 給付費(委託費)や補助金はしっかりと取れているのか【収入最大化】
- 後継者や園長をどのように育てていけばよいのか【教育・育成支援】
課題1.今後どのように運営していけばよいか【経営戦略立案支援】
まずは、最も大きな課題から見ていきます。
「将来的に子どもの人数が増える予測で、これからますます経済が良くなっていく」という時代でしたら、どのように運営していくかを考える必要はありません。
いま運営している保育事業をしっかりと行っていけば、収入的にも、資金的にも、安定して運営していくことが出来たと思います。
しかし、少子化が進む現在、しっかりと丁寧に保育を行っていれば安定して永続的に運営していくことが出来るという時代ではなくなりました。
閉園する園も増えてきたと肌で感じます。
それでは、何をするべきなのか。大げさに聞こえるかもしれませんが、保育園運営のための【経営戦略】を策定する必要があります。
- Q今後どのように運営していけばよいか。
- A
経営戦略を策定するのがお勧めです。ただ、経営戦略といっても、何十枚もあるレポートにまとめる必要はありません。
園が置かれている状況を分析し、取りうる選択肢を検討して「園としての理想を実現するためにこのように行動していく」という計画であれば、体裁はどのようなものでも構いません。
たとえば、将来を決める大きな選択肢として、施設類型があります。
一口に保育園といっても、認可保育所もあれば、認可外保育園・認定こども園もあります。それぞれの特徴をわかったうえで、「自分たちはこう進んでいくんだ!」と言えるものが、経営戦略です。

語弊があるかもしれませんが、経営戦略は「法人としての強い意志を言語化」したものだと考えています。
「これまでこうしてきたから…」「過去にうまくいったから…」という理由で進めたものは、失敗したときに時代や社会の流れを言い訳にすることが出来ます。
しかし、経営戦略を策定して進めた結果、残念なことにうまくいかなかった場合、その責任はすべて経営者に向かいます。言い訳は出来ません。
保育園経営者には「すべての責任は自分にある」という覚悟が、これまで以上に求められてくると考えています。
課題2.漠然とした経営計画はあるが、数字に落とし込めていない【財務支援】
それでは、経営戦略を策定さえすれば、どのようなものでもよいのか、という疑問が生じると思います。
しっかりと練られた経営戦略であれば、策定が終わった時点で、ある程度役目を終えている(見通しが立つ)というケースもありますが、経営戦略だけでは机上の空論になってしまいかねません。
そういったときに重要になってくるのが、数字という客観的な視点への反映(落とし込み)です。
- Q漠然とした経営計画はあるが、数字に落とし込めていない。
- A
計画があるということは、数字に落とし込むことは必ずできます。時間を取って作成するしかありません…。
社会福祉法人ですと、翌年度の予算書は毎年作っているかと思いますが、経営戦略を数字に落とし込む場合は、5年後、10年後さきまで作成すると、いま検討している計画が「実現可能なものなのか」「現実離れしているものなのか」が明確になります。
シミュレーションや予算書等の数字に落とし込むことが出来れば、これから先、成功したか失敗したかを判断することが出来ます。
毎年、5年後、10年後の予算書まで含めて経営戦略を検討し直している保育園と、経営戦略を考えず、目の前のことに必死な保育園では、どちらが安定して運営していくことが出来るでしょうか。

言葉だけの経営戦略では、とても華々しくて素晴らしいものに見えたとしても、数字に落とし込むことが出来なければ、絵に描いた餅になってしまいます。
保育事業を行う上で、5年後を見据えていくと、必ず人口動態にぶち当たります。
5年後は、いまとは全く違う状況になっているはずですが、根拠を持って検討するという作業が、将来を考えるうえでは、とても大事になります。
課題3.保育士や職員をどのようにマネジメントしていけばよいのか【マネジメント支援】
経営戦略、将来予算書の策定まで進めば、後は実現するために進んでいくのみですが、保育事業は経営者ひとりで進めることは出来ません。現場で働く保育士の先生方、管理・事務部門(バックオフィス部門)を支える職員が必要です。
- Q保育士や職員をどのようにマネジメントしていけばよいのか。
- A
ヒトの問題で悩まれている保育園では、そもそもの園として大事にしている「価値観」「決まりごと」が明確になっていないケースが多くあります。
経営者は何度も伝えているつもりでも、先生方にお話を聞くと、まったく伝わっていなかった、ということもあります。まずはマネジメントの土台を固めることからお勧めしています。
ヒトの問題で悩むのは、保育事業に限らず、すべての経営者が課題として感じているかと思います。
しかし、保育園特有だなと思うフレーズがあります。それは
- 「若い先生が多い職場だから…」
- 「女性しかいない職場だから…」
という言葉です。
しかし不思議なことに「先生方が活き活きと働いているなー!」という保育園の経営者からは、上記のような言葉は聞いたことがありません。もしこのような固定観念があるのであれば(ない方がほとんどだと思いますが)、それをなくすところから始めたほうが良いかしれません。

とても個人的な感想ですが、「女性だから…」「若いから…」という話を聞いても、それが本質ではないだろうな、と思っています。
おそらく男性が入ったとしても、同じような問題は起きるだろうな、と感じることが多いです。
組織文化の醸成、評価基準の策定、働きやすい就業体系、継続的な職員研修、などが整っている園では、やはり職員トラブルは少ないです。
ちなみに、当社では組織マネジメントに識学を取り入れています。
(参考記事:【徹底解説】識学を実際に会社経営に導入した私が解説します!怪しい?宗教?軍隊式?)
課題4.事務職員が退職したが、引継ぎがうまくいっていない【会計支援】
「保育士の人数が足りない」という話はニュースでもよく聞きますが、保育園では事務職員が退職した際の引継ぎも大きな課題になります。
保育士が足りていないという園では、そもそも開園できなかったなど大きなニュースになるので知られることがありますが、事務職員の急な退職で起きる問題はあまり表に出てきません。なぜなら「経営者が無理をして乗り越えることが出来てしまうから」です。
- Q事務職員が退職したが、引継ぎがうまくいっていない。
- A
保育士の人数が足りているかは、収入にも直結するので、しっかりと管理されている園が多いですが、事務職員については軽視されていることが多いと感じます。
事務職員については、国家資格も必要ではなく「誰でも出来る仕事」と思われがちですが、保育園の事務は、一般企業の事務を行っていたからと言って、すぐに行えるものではありません。
事務職員の退職は、園の運営に大きな影響があると認識して、いつ退職しても回るように、業務の標準化、アウトソーシングを取り入れて、事務をブラックボックスにしないことがとても大事です。
保育園の提出書類には、もちろん期限がありますが、期限が過ぎてしまったから、問答無用で受け取ってもらえない、ということは少ないです。少し期限を延ばしてもらえたりもするので、何とかこなせることも多いのですが…。
経営者が書類作成に携わっている時間は、本来なら経営者が経営者としての業務を行うはずだった時間です。短期的にも長期的にも、やはり悪い影響は出てきます。

「保育園の開園当初は自分一人で事務を行っていたから、これくらい出来るはずだ」というお話を頂くこともあるのですが、10年前と比べると、事務の難易度は格段に上がっていると感じます。
不正をする園が出るたびに、提出する書類は複雑になり、情報量が多くなっていきます。事務に対する認識が古くなっていないか、定期的な確認が必要です。
課題5.給付費(委託費)や補助金はしっかりと取れているのか【収入最大化】
当社(株式会社 いちたす)は宮城県仙台市に本社がありますが、お問い合わせを頂く園については、東北地方に限らず、全国から頂いております。
お問い合わせのなかには「このままだと園運営が成り立たない」というご相談を頂くことがあります。
来年の運営も危ういからコンサルティングを受けるための報酬を支払うことが出来ないという切羽詰まったご相談もあります。
当社では、1回1時間にはなりますが、無料相談を行っていますので、無料相談の中でも「これを行えば、ぐっと楽になりますよ」ということがあります。
- Q給付費(委託費)や補助金はしっかりと取れているのか。
- A
給付費(委託費)は、園児数が多いから安泰、少ないから苦しい、というものではありません。配置基準よりも、多く保育士を配置していれば受け取れる加算もありますし、運営方法を少し変えるだけで受け取ることが出来る補助金もあります。
もちろん、保育が中心、子どもたちが中心ではありますが、安定して運営していくためにも、制度をしっかりと理解するのはとても大事です。
「制度を上手く利用して収入を増やそうとは思いません」「保育だけを考えていたいんです」というご意見を頂くこともあり、それはとてもよくわかりますし、何のために保育事業を行っているのかにもつながっている部分ではあるのですが、そのしわ寄せは、保育園で最も大きな費用である人件費に反映(つまりは、先生方の給与が低い状況)されます。

お話をしていて、「子どもや職員について」真剣に向き合っている理事長先生の園で「保育士の賃金がとても低い」ということがあります。
処遇改善等加算を取っていなかったり、加算を取れていなかったり、理由は様々ですが、国が用意してくれている制度は利用して、先生方や園児に還元していけると良いですね。
課題6.後継者や園長をどのように育てていけばよいのか【教育・育成支援】
中小企業では、後継者不在の企業が約120万社あるということで、「大廃業時代」と社会的な問題になっていますが、保育園でも後継者不在の園は多いかと思います。
保育園を創業した理事長・園長、その後を引き継いだ2代目の理事長・園長、いろいろな保育園がありますが、50台、60代、70代の理事長先生、園長先生がほとんどだと思います。すでに自分の後を継ぐのはこのひとだ、と安心して任せられる方がいらっしゃる園は幸せですが、後継者が決まっていない園も多いと思います。
- Q後継者や園長をどのように育てていけばよいのか。
- A
日常業務をただ行っていくだけでは、後継者候補・園長候補は育ちません。教育・育成をしていくという意識が必要です。
後継者を育てるということは、これまで園として大事にしてきたこと、これからも大事にしていきたいことを棚卸する良い機会にもなります。後継者として必要な知識・スキル・心構えを、研修や実務を通して計画的に行うことで、後継者のみならず、保育園としても、とてもプラスになります。
後継者の育成は、保育園の存続にとっても大きな要素なので、育てるという意識で、数年単位で様々なことを経験できるように、道を整えていけると良いですね。

理事長先生がまだまだ現役のうちに、後継者に理事長職を譲り、ご自身は一歩距離を置いて、大所高所から意見を述べるようにして見守る、という方法を取られている園もありますが、うまくいくケースが多いです。
どうしても後継者がいない、という方には、事業承継という方法もあります。M&A仲介会社から連絡がきたという保育園も、多いのではないでしょうか。
現状は保育園経営者の相談先が少ない

先ほどのような悩みに直面した時、保育園経営者の相談相手といえば、誰でしょうか?
主な相談先を以下にまとめました。
- 「お金」の事は税理士もしくは経営コンサルタント
- 「ひと」の事は社会保険労務士
- 「法人運営・理事会」の事は司法書士または行政書士
- 他園の理事長もしくは園長
- 市町村の担当者

士業を含めた専門家には、必ず得意分野があります。
専門ではない分野については、専門家と言えど適切なアドバイスを行う事が難しいのが実情です。
保育園経営コンサルタントとは?

保育園経営コンサルタントとは
保育園経営コンサルタントとは、保育業界に特化した経営コンサルタントの事を指します。
そもそも、経営コンサルタントにはそれぞれの得意分野があります。
製造業、小売り、飲食、メーカー、アパレル … etc
ご自身の業界とコンサルタントとの得意分野がマッチする事で、保育園経営者が本当に悩んでいる事にアプローチ出来ます。

餅は餅屋と言います。
ご自身より業界に詳しくないコンサルタントに依頼すると、
余計に手間がかかり、なおかつお金が出ていく事がありますのでご注意下さい。
「コンサルタント」は、弁護士、会計士、税理士の様な国家資格が無くても「誰でも・いつでも」名乗る事が出来ます。そのため、どのような専門性があるのかという事が大事です。
保育園経営コンサルタントに依頼するメリット
ここまで、保育園経営者がどのような事に悩まされているかを説明してきました。
専門家に依頼する大きなメリットは経営者が経営者としての業務に集中出来ることと、費用対効果が大きいということです。
- 経営者が経営者としての業務に集中できる。
- 費用対効果が大きい (コストパフォーマンスが良い)。
経営者が経営者としての業務に集中できる
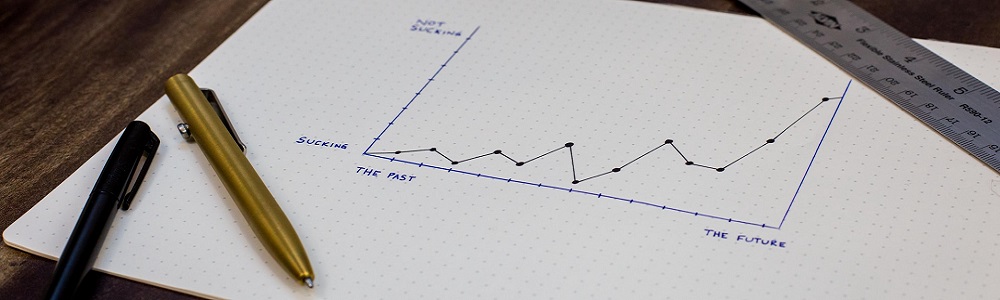
コンサルタントとして活動している者は得意分野における最新情報を常に取り入れています。
コンサルタントに依頼することで、経営者自らが最新情報を行政のHPより確認し、一生懸命資料の読み込みをしなくても、コンサルタントが経営者に情報を提供してくれる事になります。
行政の資料は難解で、量が多く、読み解くのにも時間がかかるため、経営者の方がご自身で理解をしようとすると大きな負担になります。

保育園経営コンサルタントより、分かりやすく説明を受け、ご自身の保育園に当てはめた説明を受ける事で、どれだけの時間を節約する事が出来るでしょうか?
コンサルタントに依頼することで空いた時間で、経営戦略を練ったり、保育内容の改善を行っていくことが出来ます。
費用対効果が大きい

事務職員1人の年収と専門家、どちらが低コスト?
コンサルタントと契約するという事は、余計な出費が発生すると思っている経営者は多いです。
ですが、事務職員1人を増員するコストとどちらが低コストでしょうか。
事務職員を1人雇用すると給与以外にも社会保険料、雇用保険料等出ていくお金も、手続きも増加します。法人の経営戦略に関わる事務職員を雇うとなると、高額な年収が必要になります。また、職員として雇うということは、いつ退職するかわからないというリスクを抱えることにもつながります。
コンサルタントは常に最新の情報を収集しており、その分野のプロです。
そんな特定の分野に特化した職員を雇うとなると、どれだけの年収を支払わなければならないでしょうか?
経営者の1時間をお金に換算すると?
また、事務職員を雇用せず、経営者ご自身が上記の作業を行うとなれば、どれだけのコストになるでしょうか?
経営者の方には労働時間という考え方はありませんが、それでも1時間あたりの時給を考えてみて下さい。
経営者はさらなる収入を生みだす施策や、0から1を産みだす計画を考える時間を確保する必要があるため、時給以上に大きな損失が発生している可能性があります。
企業ですと「給料の3倍稼いで一人前」と言われることがあります。
経営者は、誰でもできる業務ではなく、より付加価値の高い業務を意識して行う必要があります。
保育園経営コンサルタントに依頼する事で収入が増え、損失が減る訳
保育園・こども園の場合、園児数が減っても利用定員を変更すれば収入が増えるケースがあります。
また、毎月提出している請求書類を事務職員に任せっきりの場合、加算が抜けている可能性もあります。
市区町村は個別に指導をしてくれる事は稀なので、誤った書類を作り続け、場合によってはかなりの金額を損している場合があります。

実際に、当社がこれまでご支援をしてきた園でも、1千万円単位で収入を取りこぼしているケースがありました。
さらに、保育事業は税金についても企業とは異なるため、こちらも専門性がある税理士が担当する必要があります。
消費税の申告について、本来は非課税売上である収入を、誤って課税売上として計上し、過大に税金を支払っていた…というケースは度々起こります。
税務に関しても専門性が必要な事業という事です。
そして、恐ろしい事に損をしている事に誰も気付く事が出来ません。
株式会社いちたすでは保育事業に特化した税理士法人と提携しておりますので、税務についての課題がある場合は、税理士をご紹介することも可能です。
ご相談の対象となる方
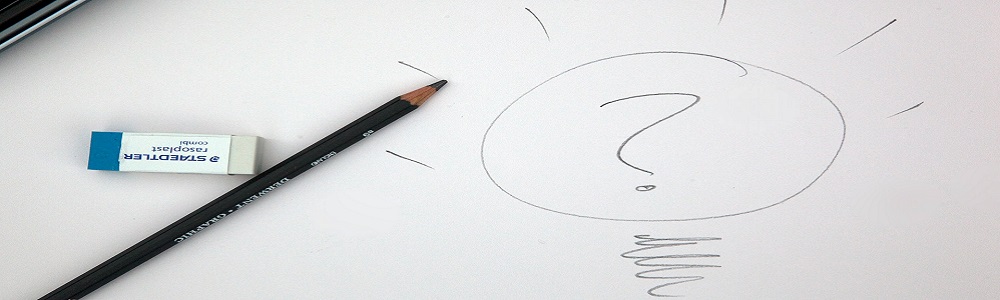

ご相談の対象となる方は「法人」もしくは「個人事業主」の経営者・事務職員の方です。
法人のお客様の例
保育事業は法人格や施設類型の組み合わせが様々で、それに伴い会計や運営のルールが異なります。
例えば、保育園経営者の方であればご存知の通り、保育園(保育所)は資金の使途制限など、知っていないと行政から指摘を受ける事がありますので、契約前に保育園のコンサル経験があるかどうか、事前に確認しましょう。
- 学校法人:私学助成園を運営
- 学校法人:幼保連携型認定こども園・施設型給付を受ける幼稚園・小規模保育園を運営
- 社会福祉法人:保育園を3園運営
- 社会福祉法人:保育所型認定こども園と企業主導型保育園を運営
- 非営利活動法人:認可外保育園と事業所内保育園を運営
- 株式会社:保育園と小規模保育園を運営
個人のお客様の例
保育園を運営されている方は、やはり法人の方が多いですが、個人でも相談をすることは可能です。
- 個人:認可外保育施設を運営
- 個人:現在保育園で勤めているが、将来保育事業を立ち上げる予定
いちたすの経営コンサルタントのご紹介
株式会社 いちたすでは、幼児教育・保育事業をされている皆様に向けて経営コンサルティング・財務支援・会計支援を専業で行っています。
専業で行っているからこそ提供できる、高い専門性を持った経験豊富なコンサルタントがご対応します。

株式会社いちたす 代表コンサルタント
大窪浩太
【中小企業診断士・AFP】
中小企業で保育園を経営されている方のみならず、学校法人、社会福祉法人、NPOといった法人格のお客様に対して、経営戦略の策定、管理会計の導入、新規園設立の支援、収入最大化などを行う。
コンサルティングの流れ


一般的なコンサルティングの流れをご説明します。
気になる事があれば、契約前にしっかり確認し、
ヒアリングの際、コンサルタントとの相性も確認する事をお勧め致します。
- 問い合わせ
解決して欲しい課題について、簡単にまとめて問い合わせしましょう。
- ヒアリング
コンサルタントより返事があり、現状の課題についてのヒアリングがあります。
経営者ご自身が感じている課題だけではなく、言語化されていない潜在課題についても明確になることがあります。 - 提案
コンサルタントから、現状の課題解決に必要なサービス、料金についての案内があります。
提案内容は現状課題に対するフルパッケージである事もありますので、全ての契約に細かい料金設定があるなら、どの契約を残して、どの契約をしないかしっかりと考えましょう。 - 見積り
提案内容に満足したら、契約したい内容をまとめてコンサルタントに連絡します。
後日、コンサルタントから見積書の提示があります。 - 契約
見積内容に問題がなければ、契約を締結します。
契約後、サービスが開始されます。
保育園経営コンサルティングのサービスメニュー


当社のサービスメニューをご紹介致します!
黄色のアンダーラインを引いているサービスが特に人気です。
- 日常業務・決算業務
- 行政監査、会計士監査
- 法人運営
- 労務
- 事業展開
サービスそれぞれに料金設定していますので、内容を切り貼りして、法人オリジナルの契約にする事ができます。
何に対してどれだけを支払っているのかが分かる契約のため、お客様にご満足いただいております。
保育園経営コンサル事例

ここで、最初にご紹介しました、経営者の方々の悩みが、当社のコンサルティングを受けられてどう変化したのかをご紹介します。
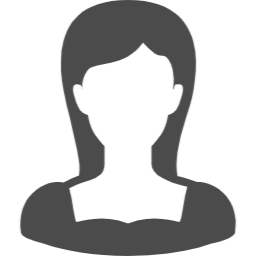
定員の変更と加算の見直しが功を奏しました。
市町村に言われるがまま、実態より大きい定員設定をしていたせいで、毎月の収入が本来よりも大きく減少している事が分かりました。さらに、配置基準以上の保育士の配置をしていたにも関わらず、加算をもらえていない事にも気が付きました。
正しい請求を行う事で、年間の収入が数100万円単位で変わる事に驚いています。
もっと早く気が付いていれば、良かったです。

職員のキャリアパスが給与と連動して皆が納得しました。
先生達のキャリアパスが可視化され、安心して当園で長く働くイメージが出来た様です。役職に対する業務も明確化されたので、職員同士のいざこざも減りました。
結果的に、離職率も下がりました。
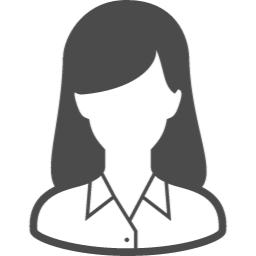
保育について考える時間が出来ました。
毎月の市町村への請求書類や処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱの資料の作成支援、日常の会計や監査対策まで、まるっと委託する事が出来るサービスが存在するなんて知りませんでした。
これでようやく、本当に時間を使いたかった園児たちのことを考えることが出来ます。
保育園コンサルティングについてよくあるご質問
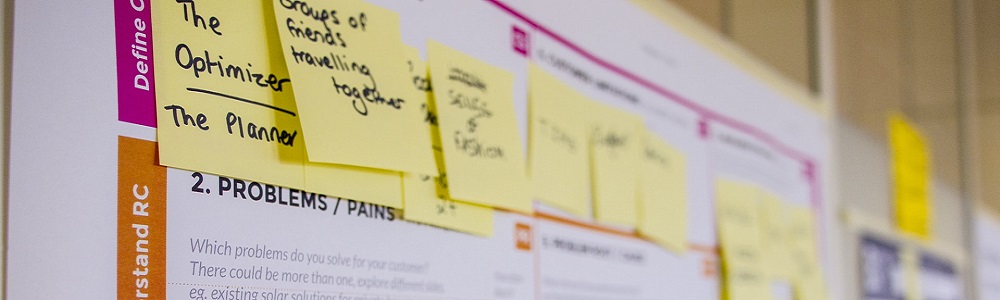
ここでは、保育園経営コンサルタントとして活動している際に、よくいただく質問をまとめました。
当社(株式会社 いちたす)としての回答にはなりますが、ご参考になれば幸いです。
- Q初回相談は無料ですか?無料の場合、どこまで具体的なアドバイスをもらえますか?
- A
弊社では、無料の経営相談を実施しています。
園の経営状況やお悩みを詳しくお伺いし、弊社の支援が可能か判断させていただきます。経営や制度に関する一般的なご質問にはお答えしますが、園で作成された個別の資料等については、無料相談での確認はできかねますのでご了承ください。
- Q無料の相談をしたら、必ず契約しなければいけないでしょうか?
- A
当社(株式会社 いちたす)では、1回1時間の無料相談を行っておりますが、無料相談内で園が抱えている課題が解決できれば、ご契約は必要ないと考えています。
ご相談内容によっては、1回では終わらない課題のこともありますので、その際は、ご契約をして継続的なご支援を提案いたしますが、貴法人にとって当社の契約が不要だと感じた場合は、ご相談に対するご回答のみと致しますので、ご安心ください。
- Q既に顧問税理士との契約があるのですが、相談は控えた方が良いでしょうか?
- A
こちらのご質問、大変よく頂くのですが、セカンドオピニオンとしてご利用いただく事も可能です。
顧問の先生と連携をしてご支援を行っている園もありますし、税理士の先生と業務内容が重ならないように業務分野を分けてご支援を行っている園もあります。法人のご希望に合わせてサービス内容を変えることも可能ですので、お気軽にご相談下さい。
- Qコンサルティングを依頼することで、具体的にどのような経営課題が解決できますか?
- A
コンサルティングは、多岐にわたる経営課題を解決します。具体的には、園児減少への対策、財務状況の改善、複雑な公定価格制度の活用、処遇改善等加算の取得、人材育成、そして多忙な経営者の時間不足解消などをサポートします。経営者が現状を客観的に把握し、未来に向けた具体的な戦略を立てる手助けをします。
- Q経営コンサルタントの費用はどれくらいかかりますか?費用対効果はありますか?
- A
費用は、依頼する内容や期間によって大きく異なります。目安とはなりますが、弊社の料金表をご確認くださいませ。また、費用対効果については、加算の取得等における収益最大化、園児募集の成功などで、コンサルティング費用を上回る収益改善が期待できます。特に、複雑な制度の専門家によるサポートは、自力で解決するよりも迅速かつ確実に成果を出せるため、費用以上の価値があると言えます。
- Q公定価格の仕組みや、処遇改善等加算など複雑な制度について、専門的なアドバイスはもらえますか?
- A
はい、可能です。弊社は、保育事業を専門とする経営コンサルティング会社のため、公定価格や処遇改善等加算、その他の複雑な加算制度を熟知しています。最新の制度変更に対応し、各園の状況に合わせて、最大限の収益を確保するための具体的なアドバイスを提供します。
- Q忙しくて経営分析や計画を立てる時間がないのですが、どのようにサポートしてもらえますか?
- A
経営者の貴重な時間を確保するため、コンサルタントが財務諸表の分析や現状の課題抽出を代行します。その上で、優先的に取り組むべき課題を提示し、具体的な改善策を一緒に考えます。また、記帳代行や処遇改善等加算の報告書作成支援といった、経営者の手を空けるサポートも行っております。これにより、経営者は日々の保育業務に集中しながら、経営の舵取りを行うことができます。
- Q園の収益を最大化するために、具体的にどのような戦略を立ててもらえますか?
- A
収益最大化のためには、「収入の増加」と「コストの削減」とのバランスが重要です。
- 収入の増加: 未取得の加算がないか診断し、新たな加算取得を支援します。また、新制度移行や新規事業の導入の検討を行います。
- コストの削減: 無駄な経費がないか診断し、適正なコスト管理を行います。
- Q今は会計支援や処遇改善の支援をお願いしたいのですが、いつかは自園で出来る体制を作りたいと考えていますが、それでも良いでしょうか?
- A
もちろん、可能です。
当社のコンサルタントから貴法人の職員に引継ぎ、もしくは当社のトレーニングを行い、貴法人の体制作りを応援致します。
- Q初めてコンサルタントを利用するのですが、どのようなプロセスで進めていくのですか?
- A
一般的なプロセスをご紹介いたします。
- 問い合わせ
解決して欲しい課題について、簡単にまとめて問い合わせしましょう。
- 無料経営相談
無料経営相談にて、現状の課題についてのヒアリングがあります。
経営者ご自身が感じている課題だけではなく、言語化されていない潜在課題についても明確になることがあります。 - サービス提案・見積提示
コンサルタントから、現状の課題解決に必要なサービス、料金についての案内があります。
- 契約
見積内容に問題がなければ、契約を締結します。
契約後、サービスが開始されます。 - 支援の実行
提案内容に基づき、具体的な支援を開始します。
必要に応じて計画を軌道修正しながら、最適なご支援をしてまいります。
まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。
教育・保育園経営でお悩みなら東北・宮城の保育業界専門経営コンサルティングいちたすへ

保育園・こども園・幼稚園を経営するうえで、お困りのことがありましたら株式会社 いちたすへお気軽にお問合せください。
今後どのように運営していけばよいか、給付費(委託費)や補助金はしっかりと取れているのかといった経営・財務に関するご相談から、保育士・職員に外部研修を行ってほしい等の人材育成に関するご相談まで、幅広くご支援しています。
いちたすについて

株式会社 いちたすでは、保育園・こども園・幼稚園の経営者の皆様に対して、経営・運営・財務に関するコンサルティングを専業で行っています。
会計事務所として、日常の会計の確認、記帳代行を行ってもいますので、保育所のバックオフィス業務、書類関係全般のご支援もしています。幼稚園・保育所・こども園の税務・労務に精通した税理士法人・社会保険労務士事務所とも提携しています。
「会計事務所は法人設立からお世話になっているから変えたくない」というお声を頂きます。
そのような場合は、会計・税務ではなく、
- 委託費の加算の取りこぼしがないか、第三者に確認してもらいたい。
- 認定こども園への移行を考えているが、何から手を付ければよいかわからない。
- 処遇改善をどのように取り入れていけばよいか、他園がどのように行っているかを知りたい。
などのお悩みに対してご支援・コンサルティングを行う顧問(相談)契約もあります。こちらは、セカンドオピニオンのようにお使いいただくことも可能です。
料金プラン
株式会社いちたすでは施設数、園児数、施設類型によって顧問料が異なりますが、必要なサービス、不要なサービスで顧問料をカスタマイズしていただける価格設定となっております。
株式会社立の保育園で、税務申告が必要の場合、税務申告は当社提携先の税理士法人と別途ご契約していただく必要がございます。
保育園単独の場合
・電話やメール、チャットでの相談契約
※セカンドオピニオンにも使えます。
・会計顧問契約
※1 決算は決算書類毎に料金を設定しておりますので、ご自身の法人で作成出来る書類がございましたら、顧問料を抑える事が出来ます。
※2 会計顧問のお客様は、自動的にお電話やメールによる運営の相談も承りますので、お得です。
※3 既に貴法人の競合園が当社のお客様である場合、契約が出来ない場合がございます。
その他業務
※その他業務につきましては、作業量により料金が異なりますので、個別の見積となります。
お気軽にお問い合わせ下さい。
依頼の流れ

お問合せフォームかinfo@ichitasu.co.jp宛にメールをお送りください。
詳しい内容をお伺いいたします。
その後は、
- 当社の担当者が園にお伺いする
- 当社事務所(仙台市一番町)にお越しいただく
- Zoomなどを利用してオンラインで打ち合わせをする
といった形で、具体的にどのようなご支援が出来るのかを打ち合わせいたします。
園によって状況は様々ですが、
など、ご要望に合わせてご提案いたします。
お気軽にお問い合わせください。