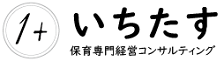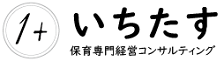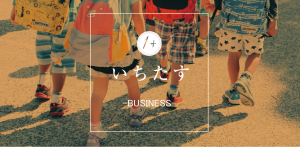現在、保育園や幼稚園を運営されている経営者の方々であっても、「幼稚園や保育園の始まり」やその「歴史」について、深くご存知の方は意外と少ないかもしれません。学校法人や社会福祉法人では、理事長先生の代替わりも進んでおり、「自分が物心つく頃には、すでに園があったので、創設の経緯を詳しく聞いたことはない…」ということもあるかもしれません。
本記事では、戦前から現代に至るまでの制度的な変遷と、それに伴う経営形態の多様化という視点から、日本の保育業界が歩んできた道のりをまとめました。歴史を振り返るということは、単なる過去を知ることだけには留まりません。現代の園経営が直面する課題を乗り越える新たな視点やヒントが、その変遷のなかに隠されていると私たちは考えます。
さらに、保育業界の会計基準の変遷といった、幼保業界に特化した経営コンサルティングを行ういちたす独自の視点からの分析も加えています。ぜひこの歴史の旅にお付き合いいただき、貴園の未来を考える一助としていただければ幸いです。
この記事を監修した人

関西の税理士法人にて公益法人に対して決算・申告書作成、財務コンサルティングを担当。 2017年、同税理士法人の仙台支店に転勤。 2019年7月に税理士法人を退職後、株式会社いちたすに参画。
得意分野:幼稚園・保育園・認定こども園の経営・財務コンサルティング。 少子化がますます進む東北で、今後数十年、安定して運営していける園づくりの支援を行う。 新規園の設立や代表者の代替わりなどの際は、法人に入り込んで、伴走型の支援を行うこともある。
宮城県中小企業診断士協会 会員
はじめに

日本の保育業界は、明治期の民間慈善事業から始まり、現在に至るまで約150年の長い歴史を歩んできました。この記事では、戦前から現代までの保育業界の変遷を、主要な法制度の改正、経営形態の多様化、会計基準の変遷などの観点から詳しく解説します。
保育業界の理解を深めることは、現在の保育制度の課題や今後の方向性を考える上で重要な基盤となります。特に、学校法人、社会福祉法人、宗教法人、個人立など、多様な経営形態の変遷と、近年の処遇改善やこども園制度についても詳しく取り上げます。
戦前の保育業界の始まり(明治期~昭和初期)

戦前、保育業界はどのようにして始まったのでしょうか。
日本初の保育施設
日本の保育業界の歴史は、明治時代まで遡ります。
- 1876年(明治9年) – 東京女子師範学校付属幼稚園が日本初の幼稚園として設立
- 1890年(明治23年) – 新潟市で赤沢鐘美・仲子夫妻による「静修女学院附設託児所」が初の保育所として開設
- 1900年(明治33年) – 東京市域で二葉保育園が貧児保育園として設立

東京女子師範学校付属幼稚園はお茶の水女子大学附属幼稚園、静修女学院附設託児所は赤沢保育園として、現在も運営されています。
戦前の保育の特徴
戦前の保育は以下のような特徴がありました。
- 民間の慈善事業 – 主に篤志家による救貧・慈善事業として開始
- 階級別の保育 – 幼稚園は富裕層、託児所は労働者階級向け
- 家族中心の育児 – 前近代的な家族制度のもと、家族ぐるみの伝統的育児が主流

幼稚園や保育園という制度が出来る前から、農繁期等で忙しい時期に、お寺で子どもを預かっていたのが、現在の幼稚園の出発点、のような園もあります。
教会が幼稚園を併設していたところもあり、いまでも母体がお寺や教会の学校法人や社会福祉法人が多いのにも戦前からの歴史があることがわかります。
法制度の整備
- 1899年(明治32年) – 「幼稚園保育及設備規程」制定
- 1918年(大正7年) – 米騒動以降、公立の保育所(公立託児所)が設立
- 1926年(大正15年) – 「幼稚園令」制定

幼稚園の数が増え制度化するよう多くの声があがったことから、幼稚園保育及設備規程が制定されました。幼稚園は満3歳から小学校就学前までの幼児を保育するところであることや幼児の人数に対する保母(保育士資格の前身の保母資格)の人数、建物や設備について規定されました。

お客様の園の人事や採用のご支援をしていくなかで
「保母資格証明書しか持っていない方だけど、以前は保育園で保育に携わっていた方なので、配置基準に入ってもらっても大丈夫でしょうか?」
というお問い合わせを頂くことがあります。
いまでは保母資格を見ることも少なくなったので、そもそもの存在を知らない方もいらっしゃいますが…(私も初めてお問い合わせを頂いたときは、しっかりと調べることになりました…)。
結論としては、2003年(平成15年)の児童福祉法の改正で、保育士が国家資格になったため、保母資格から保育士資格への登録(切り替え)を行わなければ、配置基準に入ることが出来ません。保母資格証明書では、配置に入ることが出来ず、保育士資格への切り替えにも時間が掛かるのでご注意ください。
戦後の保育制度の確立(1947年~)

戦後、児童福祉法が制定され、保育制度が確立されました。
児童福祉法の制定と影響
戦後の保育制度は、1947年(昭和22年)の児童福祉法制定により大きく変わりました。
主要な変更点
- 法的位置づけの確立 – 保育所が児童福祉施設として明確に位置づけられる
- 「保育に欠ける子ども」の定義 – 対象児童の明確化
- 公的責任の明確化 – 市町村による保育実施義務の規定
- 措置入所制度の導入 – 行政による保育所入所の決定

「保育に欠ける」という表現はネガティブな印象を受けることから、平成27年に導入された子ども・子育て新制度により、「保育を必要とする」という表現へ見直しされています。
戦後復興期の保育

保育所保育指針とは、保育の基本となる考え方や保育のねらい、また運営に関する事項について定めたものです。昭和40年の制定から令和7年10月現在までに4回の改訂があり、最新版は平成30年改訂版です。
保育所の拡大と整備(高度経済成長期)

ここでは、高度経済成長期の保育所の拡大と整備についてみていきます。
急速な保育需要の増加
昭和40年代以降、高度経済成長に伴い保育需要が急速に拡大しました。
社会背景
- 女性の社会進出 – 共働き家庭の増加
- 核家族化の進行 – 祖父母による育児支援の減少
- 都市化の進展 – 地方から都市部への人口移動
整備政策の展開
- 保育単価制の導入 – 運営費の全国的平準化
- 政策 – 保育所整備が国の重点課題として位置づけ
- 社会福祉法人への国庫補助開始 – 民間保育所の設立促進
量的拡大の成果
この時期の政策により、保育所数と受入児童数が大幅に増加し、現在の保育制度の基盤が形成されました。

歴史的に見ると、以前は幼稚園は文部省管轄の教育施設であり、保育所は厚生省管轄の福祉施設として「保育に欠ける子」を預かる施設、ということで役割が分けられているという面がありましたが…。
いまでは、認定こども園という新しい施設類型もでき、保育園児を預かる施設だから教育をしてはいけない、ということはなくなりました。
…今はなくなりましたが、以前は幼稚園で「保育」という言い方をすると、嫌がられることがありました。自分たちは保育ではなく教育をしている、という自負があったのだと思います。
ただ、私は汐見稔幸先生が「日本の幼児教育の父」と呼ばれる倉橋惣三氏の話をされているなかで
「保護+教育が幼児期の教育の本質だといっているのです。保護教育。その最初と最後の漢字を取って「保育」。だから幼児期の教育は「保育」といわなければいけないというのが、幼稚園が学校教育法に規定されたときの共通認識です」
という文章を読んで、保育にも教育という意味合いがしっかりあるんだということが分かったので、あまり使い分けはしないようにしてきました。
(出典:汐見稔幸 著「汐見稔幸 こども・保育・人間」学研プラス P37)
経営形態の多様化

現在の保育所は、多様な設置主体で運営されています。設置主体によって、保育所という制度自体に違いがあるということはありませんが、設置主体によって、特徴が異なってくるという側面はあります。ここでは、イメージを掴んでいただけるように、一般的な特徴をまとめています。
社会福祉法人
特徴
- 戦後、児童福祉法制定後の主要な経営形態
- 昭和40年代からの国庫補助により拡大
- 非営利性が特徴で税制優遇あり
- 現在も私立保育所の約70%を占める
学校法人
特徴
- 教育機関としての専門性を活かした保育
- 幼稚園との連携や一体的運営
- 非営利性が特徴で税制優遇あり
- 保育所から認定こども園に移行している園も多い
株式会社
特徴
- 法人で複数の保育所を運営している大規模・中規模法人が多い
- ICTサービスなど、新しいサービスを積極的に取り入れている
- 業務内容や管理面で、マニュアル化が進んでいる
- 土地の取得が難しい都市部に多い宗教的価値観に基づく保育理念
個人立
特徴
- 小規模で柔軟な運営
- 創設者の理念を反映
- 認可外保育所が中心
- 近年は法人化をして認可園への移行が進む
保育所保育指針の変遷

保育所の運営にとって欠かせない保育所保育指針の変遷についてです。
1965年(昭和40年)制定/最初の保育所保育指針
厚生省により初めて制定された保育所保育指針。基本的な生活習慣の確立と集団生活への適応を重視した内容でした。
主な内容
- 健康、社会、言語、自然、音楽、造形の6領域
- 保育内容の標準化
- 集団保育の基本原則
2017年(平成29年)改訂/最新の保育所保育指針
現代の子育て環境や発達科学の知見を踏まえ、子どもの主体性と創造性を重視する内容に発展。
主な変更点
- 3つの柱(知識・技能、思考力・判断力・表現力、学びに向かう力・人間性)
- 5領域の再構成(健康、人間関係、環境、言葉、表現)
- 幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿
- 保護者支援の明確化
改定の変遷
| 年度 | 主な改訂内容 |
|---|---|
| 1965年 | 初制定(6領域) |
| 1990年 | 第1次改訂(養護的機能の明確化) |
| 2000年 | 第2次改訂(地域子育て支援機能の追加) |
| 2008年 | 第3次改訂(保育所保育指針の告示化) |
| 2017年 | 第4次改訂(幼保小連携の強化) |
規制緩和と株式会社参入(2000年以降)

これまで市町村か社会福祉法人に限定されていた保育所設置の制限が撤廃されました。

保育園の歴史を見ていくうえで、規制が緩和され、株式会社でも認可保育所を運営できるようになったことは、とても大きな転換点でした。
それまでは地域に根差した社会福祉法人が、ひとつの園か2,3の園を運営する形態が多かったですが、株式会社の参入により、ひとつの法人で数十園、100園単位で運営する法人が出てくるようになりました。
2000年の規制緩和
背景
- 待機児童問題の深刻化
- 多様な保育ニーズへの対応
- 競争による保育の質向上への期待
主な変更点
- 保育所設置主体の制限撤廃(従来は市町村・社会福祉法人に限定)
- 株式会社、NPO法人、学校法人などの保育所運営が可能に
株式会社参入の現状
参入状況
- 2000年以降、段階的に参入が拡大
- 令和4年度時点では、私立保育所の約11%が株式会社運営
- 特に都市部での参入が顕著
メリットと課題
メリット
- 効率的な経営手法の導入
- 迅速な意思決定
- 革新的な保育サービスの提供
課題
- 営利性と保育の質のバランス
- 継続的な運営の担保
- 地域との連携強化の必要性
認定こども園制度の成立(2006年)

認定こども園制度ができたことで、これまで保育園ではなかなかできなかった独自の保育内容を認定こども園に移行すればできるようになりました。これまでは、幼稚園は教育、保育園では保育(預り)という位置づけだったものが、その境目が曖昧になり、教育と保育の一体化がよりいっそう重視されるようになりました。
制度創設の背景
- 少子化の進行
- 就労形態の多様化
- 幼稚園と保育所の機能的重複
社会的背景
認定こども園の特徴
4つの類型
- 幼保連携型 – 幼稚園と保育所の機能を併せ持つ単一施設
- 幼稚園型 – 幼稚園が保育所機能を追加
- 保育所型 – 保育所が幼稚園機能を追加
- 地方裁量型 – 地方独自の基準による施設
2015年子ども・子育て支援新制度
主な変更点
- 幼保連携型認定こども園の法的位置づけを「学校及び児童福祉施設」として明確化
- 財政措置の一元化(施設給付型)
- 認可・指導監督の一元化
普及状況
| 年度 | 施設数 | 主な動向 |
|---|---|---|
| 2007年 | 105施設 | 制度開始 |
| 2015年 | 2,836施設 | 新制度開始 |
| 2023年 | 9,220施設 | 着実な増加 |

いまでは待機児童が全国的にも解消されてきていますので、認定こども園移行を国が推し進めるという感じではなくなっていますが…。
認定こども園の制度が動き始めた当初は、保育園だけではなく幼稚園にも、待機児童が多かった1歳児、2歳児を預かってもらえるようにして、待機児童解消を狙っていた感がありました。
ただ、幼稚園が保育園児の1歳、2歳を受け入れようとすると、そのままでは給食設備などの施設要件を満たすことが出来ず、11時間開園というハードルもあり、思うように、幼稚園からこども園への移行が進まなかったという実態がありました。
そこで、待機児童解消のために、小規模保育事業所や企業主導型保育所、新規の保育所の開園が進み、結果的にいまの施設数が多い供給過多の状況になってしまったと感じています…。
保育業界の会計基準の変遷

続いて、会計基準といった目線から、保育業界を捉えます。
歴史的変遷
1950年代~
- 社会福祉事業法(現在の社会福祉法)制定により社会福祉法人会計の基礎が成立
- 1970年代に経理規程が整備
現代の会計基準
社会福祉法人会計基準
特徴
- 平成12年(2000年)に統一基準として整備
- 事業区分別・拠点区分別の会計処理
- 非営利性を重視した会計処理
主要項目
- 資金収支計算書
- 事業活動計算書
- 貸借対照表
学校法人会計基準との違い
| 項目 | 社会福祉法人 | 学校法人 |
|---|---|---|
| 基本金 | あり(第1号~第3号) | あり(第1号~第4号) |
| 計算書類 | 資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表 | 資金収支計算書・事業活動収支計算書・貸借対照表 |
| 特徴 | 福祉事業重視 | 教育事業重視 |

社会福祉法人も学校法人も、営利性ではなく継続性を重視しますので、企業会計でいう利益がわかる事業活動計算書ではなく、支払資金がいくらあるかという資金収支計算書が重視されています。
統一化への取り組み
社会福祉法人会計と学校法人会計の統一化について、課題と方向性を確認します。
課題
- 経営形態により異なる会計基準
- 比較可能性の欠如
- 透明性の確保
今後の方向性
- より透明で比較可能な会計基準の整備
- デジタル化への対応
- 国際会計基準との整合性

社会福祉法人も学校法人も、そもそもの成り立ちや考え方が違い過ぎるので、そう簡単には会計基準が統一されることはないとは思いますが…。
ただ、資金収支と事業活動、名前は似ているのに、計算書類としてはかなり見え方が異なりますので、統一したほうが誰が見てもわかりやすい決算書になるとは思います。
ただ、学校法人の理事会・評議員会の考え方が、社会福祉法人の考え方に寄っていってはいるので、法人設立の目的は違えど、具体的な実務は統一されたほうが、効率化が進むのは間違いないです。
処遇改善や近年の改革(21世紀)

処遇改善等加算制度やこども家庭庁の創設等、近年の制度改革についてです。
保育士の処遇改善
処遇改善等加算の変遷
2013年度~
- 保育士処遇改善加算の開始
- 段階的な加算額の拡充
2017年度~
- キャリアアップ研修と連動した処遇改善加算Ⅱを導入
- 副主任保育士・専門リーダー等の新たな職階の創設
2024年度
- 過去最大幅の10.7%の給与改善(人事院勧告分)を実施
2025年度
- 処遇改善等加算一本化
処遇改善の効果
給与水準の向上
- 2013年度と比較して月額7万円以上の改善
- 全産業平均との格差縮小
質の向上
- 研修機会の拡充
- キャリアパスの明確化
- 離職率の改善
こども家庭庁の創設(2023年)
設立の意義
- 子ども政策の一元化
- 縦割り行政の解消
- 子どもの視点に立った政策立案
主要政策
- こども未来戦略の策定
- 異次元の少子化対策の推進
- 保育の質と量の両面での充実
その他の重要な改革
保育無償化(2019年)
対象
- 3~5歳児:全世帯
- 0~2歳児:住民税非課税世帯
効果
- 保育利用の拡大
- 家計負担の軽減
デジタル化の推進
主な取り組み
- 保育ICTシステムの導入支援
- 事務負担の軽減
- 保育の質向上への活用

労働人口の減少で、なかなか採用が出来ない、求人を出しても応募者が来ないということはすでに起き始めています。保育を行うのはひとですが、ひとが行わなくても良い部分にはICTシステムを導入する、文章を書く際は生成AIを導入するなど、効率化できる部分をいかに効率化していくかが大事になってきています。
まとめ・今後の展望

歴史的変遷の総括
日本の保育業界は、明治期の民間慈善事業から始まり、戦後の児童福祉法制定を経て公的保育制度が確立されました。高度経済成長期に大きく拡大し、2000年以降の規制緩和により多様な経営主体が参入するという歴史的変遷を辿ってきました。
経営形態と制度の発展
社会福祉法人中心の体制から、学校法人・宗教法人・株式会社など経営形態が多様化し、保育施設の類型も増えました。これからは保育の質の確保と経営効率化の両立が、ますます重要な課題となってきています。
今後の展望
少子高齢化社会における保育業界の今後は、以下の点が重要な展望となります。
- 処遇改善の継続 – 保育士の確保と質の向上
- こども家庭庁による一体的支援 – 省庁横断的な子育て支援
- 多様な保育ニーズへの対応 – 働き方改革に対応した柔軟な保育サービス
- デジタル技術の活用 – 効率化と質の向上の両立
- 地域との連携強化 – 子育て支援の地域ネットワーク構築
最後に
日本の保育業界は、時代の変化に応じて進化を続けてきました。今後も、子どもたちの最善の利益を第一に考えながら、持続可能な保育制度の構築に向けて、関係者一同が協力していくことが求められています。
参考文献・出典
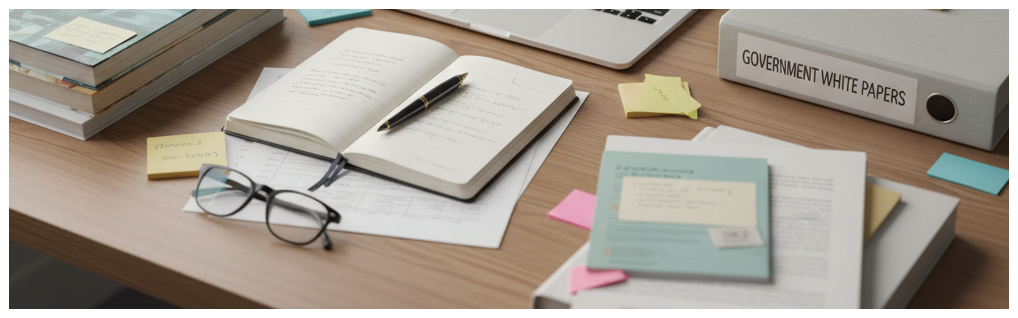
- 厚生労働省「保育所保育指針の策定及び改定の経緯」
- こども家庭庁「よくわかる「子ども・子育て支援新制度」」
- 文部科学省「幼稚園の整備」
- 各年度「保育白書」
- 「戦後日本の保育所制度の変遷-児童福祉法1997年改正までの軌跡を中心に」学術論文
- 「保育所保育の歴史 : 昭和30年代の大阪市を中心に」学術論文
- 東京都練馬区「保育の歴史とこれから~長期的な視点から保育サービスを考えるために~」
保育園・幼稚園・こども園経営のご相談なら幼児教育・保育専門コンサルティング会社いちたすへ

保育園・こども園・幼稚園を経営するうえで、お困りのことがありましたら株式会社 いちたすへお気軽にお問合せください。
人事院勧告分への対応はもちろん、処遇改善等加算の配分方法や、今後どのように運営していけばよいか、給付費(委託費)や補助金はしっかりと取れているのかといった経営・財務に関するご相談から、保育士・職員に外部研修を行ってほしい等の人材育成に関するご相談まで、幅広くご支援しています。
いちたすについて

株式会社 いちたすでは、保育園・こども園・幼稚園の経営者の皆様に対して、経営・運営・財務に関するコンサルティングを専業で行っています。
会計事務所として、日常の会計の確認、記帳代行を行ってもいますので、保育所のバックオフィス業務、書類関係全般のご支援もしています。幼稚園・保育所・こども園の税務・労務に精通した税理士法人・社会保険労務士事務所とも提携しています。
「会計事務所は法人設立からお世話になっているから変えたくない」というお声を頂きます。
そのような場合は、会計・税務ではなく、
- 委託費の加算の取りこぼしがないか、第三者に確認してもらいたい。
- 認定こども園への移行を考えているが、何から手を付ければよいかわからない。
- 処遇改善をどのように取り入れていけばよいか、他園がどのように行っているかを知りたい。
などのお悩みに対してご支援・コンサルティングを行う顧問(相談)契約もあります。こちらは、セカンドオピニオンのようにお使いいただくことも可能です。
料金プラン
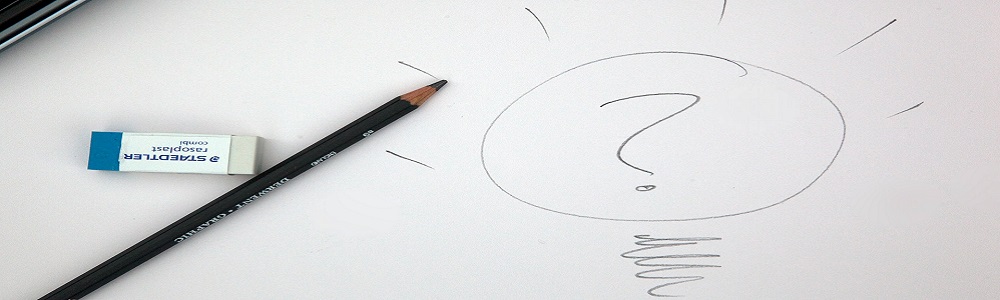
株式会社 いちたすでは、定期的な顧問契約から、スポット(単発)での委託費の確認、申請書類の確認なども行っております。
たとえば相談契約、コンサルティング契約ですと
で引き受けております。
「複数施設を運営しているが本部で契約したい」「打ち合わせは2か月に1回でよい」など、オーダーメイドでご契約内容を作成いたしますので、お気軽にご連絡ください。
依頼の流れ

お問合せフォームかinfo@ichitasu.co.jp宛にメールをお送りください。
詳しい内容をお伺いいたします。
その後は、
- 当社の担当者が園にお伺いする
- 当社事務所(仙台市一番町)にお越しいただく
- Zoomなどを利用してオンラインで打ち合わせをする
といった形で、具体的にどのようなご支援が出来るのかを打ち合わせいたします。
園によって状況は様々ですが、
など、ご要望に合わせてご提案いたします。
お気軽にお問い合わせください。